孫子は、今から約2,500年前にあたる、紀元前500年ごろの斉国(現中国の一部)で、孫武(書籍内でいう孫子と同一人物)という人物によって書かれた兵法書です。時代を超えて内容が評価され、2,500年もの間、世界中で多くのリーダーから読み継がれてきた孫子は、全部で十三篇から構成されます。
今回はそんな孫子の中から、第三:謀攻篇)を簡単にご紹介!
これはテスト勉強ではありません!
なので、まずは知ることを楽しめればそれでヨシ!ついでにリーダーとして役に立つ何かを学べれば、もっとヨシ!「ふ~ん」っていうような、気楽なきもちで見てみてくださいね♪
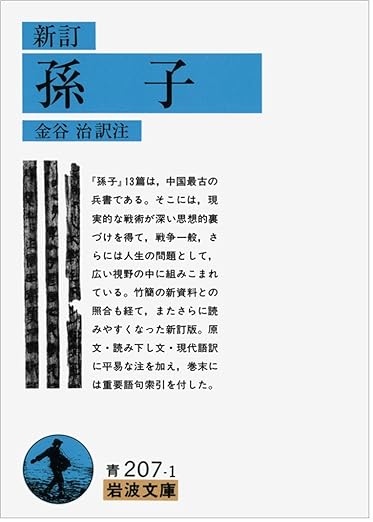
金谷治訳注 新訂孫子 岩波文庫
第三:謀攻篇 結論
利益を最大にする方法を知っているか?
戦って必ず勝つだけでは、まだ足りない。
無傷のまま勝つ。これが利益の最大化だ。
「謀攻篇」という言葉の意味
今回も、まずは「謀攻篇」という名前の意味の確認から行ってみましょう!現代でも見かける漢字なので、なんとなくイメージが付く方もいるかもしれませんが、確認は大事なのですっ!
ε-(`・ω・´)フン!!
そして、「謀攻」という熟語の形になっているので、第二:作戰篇の時にも活用した、漢字分解の術を使って「謀」と「攻」に分解してから意味を調べます。ちなみに、まだ第二:作戰篇をご覧になっていないよ~っていう方は、ぜひそちらを先に読んでみて下さい!今回の第三:謀攻篇に繋がるお話で、より本記事の理解が深まると思います!
謀は、謀る / 計画をする / はかりごと / 計略 などの意味を持つ漢字です。
引用元:漢字辞典ONLINE. 漢字「謀」の部首・画数・読み方・筆順・意味など
攻は、攻める / 攻撃する / 敵をうつ などの意味を持つ漢字です。
引用元:漢字辞典ONLINE. 漢字「攻」の部首・画数・読み方・筆順・意味など
いつもありがとう、漢字辞典ONLINE。君、本当に頼りにしてるよ。
…と、漢字辞典ONLINEへの感謝を口にしたところで、「謀」「攻」それぞれの漢字の意味をくっつけて考えてみると、「はかりごとによって敵を攻める」という意味になります。
はかりごと、つまり前もって何かしらを考えることですね。おや…?第一:計篇の時にも見かけた説明になりましたね。つまりこの章では、何を考えるのか、ということがまた大事になってきます。その考えの先に、敵の攻め方を描いていくということなんですね。
最上の勝利とは
孫子の第三:謀攻篇では、最上の勝利について次のように説明されています。
原文)不戦而屈人之兵、善之善者也。
書き下し文)戦わずして人の兵を屈するは善の善なる者なり。
現代語訳)
戦闘しないで敵兵を屈服させるのが、最高にすぐれたことである。
引用元:金谷治訳注 新訂孫子 岩波文庫 P45 – 46
孫子は兵法書って聞いていたのに、戦わないことが最高とか、ま~たこの本はなに言ってるんだよ…と思ったそこのあなた!はい、私もそう思います(笑)
けれども、第二:作戰篇の内容をちょ~っと思い出してみてください。「時間も人材も資材も無限じゃないから使い方が大切なんだよ」ということが書いてあったと思います。そう考えると、目線が変わってきませんか?
そう、最初から戦わなければ、何も失うことはないのです!つまり、無傷の勝利が手に入る、ということです!
もちろん、そんな毎回都合よく戦わずに済む、ということはないと思います。ただ、戦わないことこそ至高、という発想を持っていれば、あとは最低限どの手段をつけ足して勝利を目指すのか、という考え方を持つことができます。
この考え方は、普段学校のテストのために勉強したり、仕事のために新しい方法を考えたりする我々も、しっかりと学ぶ必要があるものかと思います。
例えば、仕事を例にとって考えてみましょう。
新たな業務が増えそうなとき、新しいシステムを次々に導入する方がいらっしゃいます。一つ一つのシステムは確かに魅力的な機能を持っていたりして、それらをどんどん導入してうまく使うことで、一見新しい業務は簡単に潮流に乗るのではないかと思ってしまいます。
けれども、この例だと実は働いている仲間がつらい思いをしている場合も多々あると思うんです。その理由の一つに、システムが必要以上の性能であり、過剰であるということが考えられると思います。
過剰な性能というのは、男のロマンとして考えるなら非常にワクワクするものですが、誰かにとってはシステムを使うために必要な勉強量が増え、負担になってしまいます。
そう考えた時、何もしないことを最上とする思考方法は、負担を感じていた人にとって救いになると思いませんか?業務のために学ぶものは、余すことなく業務に使える。必要になったら、その時に学ぶ。
だからこそ、何もしないことを最上として、その上で必要最低限を考える、という孫子に書いてある姿勢が現代の私たちにも大いに役立つものなのではないかと感じました。
彼れを知りて己れを知れば、百戦して殆うからず
これまでの話で、最上の勝利とはどのようなものかが分かったと思います。
そして、第三:謀攻篇には、孫子を語る上で外せないもう一つの有名な言葉があるので、ここで取り上げようと思います。
原文)知彼知己者、百戰不殆。
書き下し文)彼れを知りて己れを知れば、百戦して殆うからず。
孫子の中でも屈指の有名なこの言葉、聞いたことがある!と思った方もいらっしゃったのではないでしょうか?
相手を知り、自分を知れば、百回戦ったとしても危険はない。
この文章の直前には、勝利を知るために必要な要素が列挙されています。そして、相手と比べるものは五つ紹介されているのですが、私はその内容を見た時に、「あれ、第一:計篇で見かけた五事七計と内容が似ているな」と思いました。
ということで、ここでは計篇から七計の内容を再掲して、相手と比べるものを復習しようと思います。
一.君主が人々から支持されているか
(組織の重役がメンバーからの支持を集めることができているか)
二.将軍が有能であるか
(リーダーが有能であるか)
三.天候、土地の状況が優れているか
(タイミング、場面が適切か)
四.法令が正しく執り行われているか
(規律がしっかりとしているか)
五.軍は強いか
(チームとしての力が高いか)
六.兵士がよく訓練されているか
(チームのメンバーにも実力があるか)
七.賞罰がはっきりとした基準に基づき執り行われているか
(何をしたら褒められる、何をしたら怒られる、その基準がはっきりとしているか)
今、このように七計の内容を引っ張ってきました。そして、第三:謀攻篇の内容も反映して七計について考えてみると、ここまでの流れを次のようにまとめることができると思います。
一番いいのは、何もしないことである。
その思想のもと、必要最低限が何かを考える。
必要最低限を考えてみたら、五事七計に当てはめて、相手と自分のことを知る。
このようにして相手と自分のことを知ったうえで始めた戦いでは、負けることはない。
おわりに
皆さんはこれまで、最上の勝利ってどういうものか考えたことはありましたか?私は孫子を読んだことで、敵を倒す以外に、何もしないことを最上とする考え方があるということを知り、非常に衝撃を受けました。
戦い方を書くはずの兵法書において、戦わないという考え方を書く…まさに逆転の発想ですよね。
スゴ(๑°ㅁ°๑)!!‼
このような逆転の発想は、きっと思考が沼に陥りそうな時にこそ真価を発揮するものだと思います。間違いなく今後の私たちにも生きる考え方だと思うので、ねころびながらでも何回も目にして頭の片隅に入れておきたいと私も思います。
では今日はここまでっ!読んでくださってありがとうございました!
おやすみなさい~~ ꜂( ꜄.ω.)꜄コテン

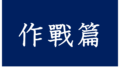
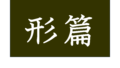
コメント