孫子は、今から約2,500年前にあたる、紀元前500年ごろの斉国(現中国の一部)で、孫武(書籍内でいう孫子と同一人物)という人物によって書かれた兵法書です。時代を超えて内容が評価され、2,500年もの間、世界中で多くのリーダーから読み継がれてきた孫子は、全部で十三篇から構成されます。
今回はそんな孫子の中から、第二:作戰篇)を簡単にご紹介!
これはテスト勉強ではありません!
なので、まずは知ることを楽しめればそれでヨシ!ついでにリーダーとして役に立つ何かを学べれば、もっとヨシ!「ふ~ん」っていうような、気楽なきもちで見てみてくださいね♪
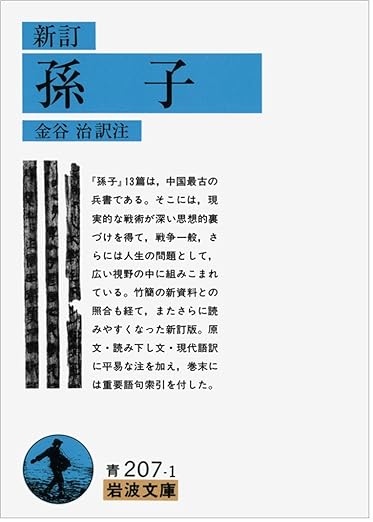
金谷治訳注 新訂孫子 岩波文庫
第二:作戰篇 結論
時間は、無限じゃない。
人材は、無限じゃない。
資材は、無限じゃない。
だから、使い方が大切なんだよ。
孫子の言う、「作戦」
孫子は、日本語みたいにひらがなとかカタカナは使われておらず、漢字だけで書かれた書物です。そして、普段私たちが使わないような漢字もよく出てくるので、章のタイトルを見ても何を表した部分なのか分からないことも…(´・ω・`)ショボーン
そんな中、この章のタイトルは「作戰篇」!「作戦」という言葉であれば、現代でもよく耳にしますよね。何をしようかな~と計画を立てたり、どうやったら勝てるかな~と考えたりする様子を表す言葉ですね。
そっか「作戰篇」かぁ~。兵法書に出てくる作戦なんだから、どうやって相手を倒すのかとかが書いてあるのかな~。そう思うじゃないですか。
ところがどっこい。ここでは違いまっせ。
∑( ◦д⊙)‼エッ
まぁ、戦いのために考えていることには変わりないんですよ。けど、勝つために考えているんじゃないんです。
どうなったら自分たちは苦しいだろうか、これを考えるんですよ。
…(-ω- ?)ドユコト?
故兵聞拙速、未賭巧之久也 ~過去に学べ~
「拙速(せっそく)」と「巧久(こうきゅう)」
どうなったら自分たちは苦しいだろうか。そのことが分かりやすく示された文章が作戰篇にはあります。
原文)故兵聞拙速、未賭巧之久也。未兵久而國利者、未之有也。故不我盡知用兵之害者、則不能盡知用兵之利也。
書き下し文)故に兵は拙速なるを聞くも、未だ巧久なるを睹ざるなり。夫れ兵久しくして国の利する者は、未だこれ有らざるなり。故に尽〻く用兵の害を知らざる者は、則ち尽〻く用兵の利をも知ること能わざるなり。
うーん、原文とか書き下し文でこの部分を見ると、実に難しい!
どうやら意味を知るためには、「拙速」「巧久」という難しい言葉の意味を調べる必要がありそうですね。
まずは「拙速」の意味から。
できはよくないが、仕事が早いこと。また、そのさま。
引用元:goo辞書. 拙速(せっそく)とは? 意味・読み方・使い方をわかりやすく解説 – goo国語辞書
φ(・ω・ )フムフム…つまり「上手くはないけど早い」ってことですね。
では次に、「巧久」の意味について。実はこの言葉、そのまま調べても辞書とかではなかなか見つからなくて困っちゃいます…そんな時は、「巧」と「久」の漢字に分解して調べてみましょう。漢字分解最強っ!
巧は、たくみ / わざ / 技術 / うまい / 上手 / いつわり / うわべだけを飾る などの意味を持つ漢字です。
引用元:漢字辞典ONLINE. 漢字「巧」の部首・画数・読み方・筆順・意味など
久は、久しい / 久しくする / 長い / 昔からの などの意味を持つ漢字です。
引用元:漢字辞典ONLINE. 漢字「久」の部首・画数・読み方・筆順・意味・成り立ちなど
ほぅほぅ( *゚д゚))
上で調べた「巧」「久」の意味をいいとこどりして考えると、「上手くて長い」という意味になりますね。
ここまでで調べた「拙速」「巧久」の意味を整理すると次のようになります。
「拙速」:上手くはないけど早い
「巧久」:上手くて長い
ほ~ん、では逆の意味の言葉が並んでたのね。
そして、文章としては「戦争の場面で拙速は聞くけど、巧久は見かけないよ」と言っています。つまり、「戦争を考える時に、上手くはないけど早い、という話は耳にするけど、上手いけど時間がかかる、という話は見かけないよ」ということです。
数に限りのあるものだから考えるんだよ
「戦争を考える時に、上手くはないけど早い、という話は耳にするけど、上手いけど時間がかかる、という話は見かけないよ」ということが述べられていたようですが、これはなぜでしょうか?それは、戦争とは自分と相手がお互いに人同士で争うものだからです。時間がかかればかかるほど、傷ついてしまう兵士が増えてしまいます。戦うための道具だってどんどん壊れてしまいます。兵士が戦場で過ごすための食糧だって、たくさん必要になってしまいますよね。
そして、今挙げた例はどれも数に限りのあるものなんです。時間をかければかけるほど、その限りあるものは失われていく。味方が苦しむ羽目になる。そういう意味では、ボーっと過ごすだけなら有り余っているように感じてしまうような時間だって、戦う場面では貴重で限りあるものになります。
このように、色々と数に限りがあるから戦争が長引くのは良くないことなんだよ、ということが述べられていました。さらに、孫子では数に限りがあることを理解した上で、どう対処していくのかということについても書かれています。書かれてはいるのですが、まぁこれもまた面白くて、ズバリ、できるだけ相手から奪ってしまえ!
え、孫子って兵法書なのに序盤から相手のものを奪うこと考えるの!?とちょっと驚いてしまいますよね(笑)
ところが、これってとても合理的なんです。だって自分たちが持っているものは限られているけれども、奪ってしまえばその分失わずにすむんです。それどころか、私たちは人間なので心があり、モノを失わないということはモチベーションを保つことにも繋がるんです。兵法ってすごいな…
さらにさらに、このような判断ができる人物が私たちのリーダーならどうでしょうか?勝利のために、優れた手段を選択できるリーダーです。限りがあることを知っているリーダーです。きっとものすごく頼りにしてしまうでしょうし、実際に成果も残してくれそうですよね。
こういう優れたリーダーが、あるチームにはいて、あるチームにはいなかったとしたら?きっと優れたリーダーがいるチームが勝つでしょう。つまり、リーダーの良し悪しがメンバーの行く末まで決めるわけです。
孫子を記した孫武も、そのことを認識していたのだと思います。だから、作戰篇の最後にこのような文章を記したのだと思います。
原文)故知兵之將、生民之司令、國家安危之主也。
書き下し文)故に兵を知るの将は、民の司令、国家安危の主なり。
現代語訳)
以上のようなわけで、戦争〔の利害〕をわきまえた将軍は、人民の生死の運命を握るものであり、国家の安危を決する主宰者である。
引用元:金谷治訳注 新訂孫子 岩波文庫 P42 – 43
おわりに
「作戰篇」では、数に限りがあることを知って、そのうえで考えることが大切である旨が書いてありましたね。そして、その考えをもとに今やろうとしていることの利害を考えるリーダーの存在が、組織の命運を左右するのだ、ということも最後に触れられていましたね。
数に限りがあるという点では、私たちにも大きく重なる部分があるのではないかと思います。一日は二十四時間だし、気力にも限界があるし、財力にだって限界がある。この限界を考えたうえで、どういう選択をするのか。さらに仲間がいる場合なら、仲間の限界を考えたうえで、チームとしてどこを到達点に設定するのか。難しいことですが、だからこそ毎日ちょっとでも考えることが大切なのかなと思います。
…てことはですよ、今これ読んでくださってるそこのあなた!えらい!めっちゃえらい!なでなでしてあげます!
ナデナデ( ̄▽ ̄)ノ”(^∇^) (^∇^)ヾ( ̄▽ ̄)ナデナデ
ではおふざけ成分も増えてきたことですし、今日はここまでっ!読んでくださってありがとうございました!
おやすみなさい~~ ꜂( ꜄.ω.)꜄コテン



コメント