孫子は、今から約2,500年前にあたる、紀元前500年ごろの斉国(現中国の一部)で、孫武(書籍内でいう孫子と同一人物)という人物によって書かれた兵法書です。時代を超えて内容が評価され、2,500年もの間、世界中で多くのリーダーから読み継がれてきた孫子は、全部で十三篇から構成されます。
今回はそんな孫子の中から、第四:形篇)を簡単にご紹介!
これはテスト勉強ではありません!
なので、まずは知ることを楽しめればそれでヨシ!ついでにリーダーとして役に立つ何かを学べれば、もっとヨシ!「ふ~ん」っていうような、気楽なきもちで見てみてくださいね♪
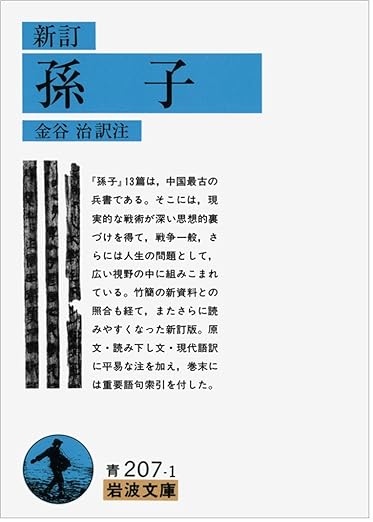
金谷治訳注 新訂孫子 岩波文庫
第四:形篇 結論
自分にできる準備を済ませ、待ち構えよ。
そして、ここぞのチャンスを逃さず動け。
これが、先に勝利を得るということだ。
「形篇」という言葉の意味
まずは、毎度毎度のタイトル確認から!「形篇」という名前に含まれる、漢字「形」の意味について見てみましょう。
形は、かたち / ありさま / からだ などの意味を持つ漢字です。
引用元:漢字辞典ONLINE. 漢字「形」の部首・画数・読み方・筆順・意味など
「形」という漢字は、小学校でも習うものなのでなんとなくイメージが湧きやすいですね!今回の場合は、そのまま「かたち」という意味でOK!
では、ここでいう「かたち」とはなんのこと…?
答えは、「軍隊の形」です!兵法書なのに物理的な戦闘以外がここまで多く述べられていた孫子において、やっと兵法書らしい内容が出てきた気がしますね(笑)
話を戻して、つまり形篇は軍隊の形について述べた章ということになります。
そっか、軍隊の形について述べた章ならば、どのような形に兵士を配置すれば強い陣形が作れるのかとか書いてあるのかな~と思いきや。
察しの良い方であれば、もう分かるはず。はい、そんなにストレートに書いてくれないのが孫子です(笑)
形篇でも、どのような陣形が優れているのかとか、そのようなことは書いていません。残念っ!では今回はどこに着目するのでしょうか?
基本は守備だ ~主導権を握るのは誰か~
孫子の第四:形篇は、次のような文章から始まります。
原文)孫子曰、昔之善戰者、先爲不可勝、以待敵之可勝。
書き下し文)孫子曰わく、昔の善く戦う者は、先ず勝つべからざるを為して、以て敵の勝つべきを待つ。
現代語訳)
孫子はいう。昔の戦いに巧みであった人は、まず〔身方を固めて〕だれにもうち勝つことのできない態勢を整えたうえで、敵が〔弱点をあらわして〕だれでもがうち勝てるような態勢になるのを待った。
引用元:金谷治訳注 新訂孫子 岩波文庫 P56
第四:形篇はこのように、まずは守りを固めることを第一歩とした話から始まります。
守りを固めて、揺らぐことのない安定した土台を作る。その頼れる土台を作ったうえで、敵側に攻め込む隙が生まれて勝機が見えた時を待つんですね。
これについては、人により考え方が分かれる場所かもしれません。例えば、「攻撃は最大の防御」という言葉がありますが、このようにイケイケ思考の方にとってはなぜ最初に守るのかと思われるでしょう。
なぜ戦い上手な人は最初に守るのか。その理由について、孫子ではこのように述べられています。
原文)不可勝在己、可勝在敵。故善戰者、能爲不可勝、不能使敵之可勝。(中略)不可勝者、守也。可勝者、攻也。
書き下し文)勝つべからざるは己れに在るも、勝つべきは敵に在り。故に善く戦う者は、能く勝つべからざるを為すも、敵をして勝つべからしむること能わず。(中略)勝つべからざる者は守なり。勝つべき者は攻なり。
現代語訳)
だれにもうち勝つことのできない態勢〔を作るの〕は身方のことであるが、だれもが勝てる態勢は敵側のことである。だから、戦いに巧みな人でも、〔身方を固めて〕だれにもうち勝つことのできないようにすることはできても、敵が〔弱点をあらわして〕だれでもが勝てるような態勢にさせることはできない。(中略)だれにもうち勝てない態勢とは守備にかかわることである。だれでもがうち勝てる態勢とは攻撃にかかわることである。
引用元:金谷治訳注 新訂孫子 岩波文庫 P56
そう、守備は自分から変えられる部分なんです!
一方、攻めは相手の状態の影響を受ける部分です。
自分から変えられるものと、相手の様子をうかがって反応を変える必要があるもの。この二つについて、どちらを優先して考えるのか、ということですね。
そして、孫子ではその問題の解決策として、先に自分から変えることのできる守備を整えて準備を済ませる。そして、相手の態勢が不安定となり攻め時となるまで焦らずに待ち、相手の態勢が崩れて誰でも勝てるような状態になったところで攻めに転じろ、と説明されているワケですね。
うん、言わんとすることは分かる。分かるけれども、明らかに、その攻め時を見極めるのは難しそうじゃ…
((+_+))ウーン
この側面については、実際に孫子の中でも、「戦い上手と言われた人々は、他の多くの人々が気が付くことのできない絶好のタイミングを見極め、そのタイミングで攻めることによって勝利を得ていた」という旨の記載があります。
つまり、「積極的に動くべきタイミングで動くことができる人は、戦い上手である」と言うことができそうですよね。
「積極的に動くべきタイミングで動けって、やっぱりそれ一般人には難しいやつじゃね?」と思われたそこのあなた、まぁまぁお待ちくださいませ。ここからが第四:形篇の内容を現代に置き換えた時の裏テーマなんじゃないかと思っている部分になるのでぜひ見ていって下さいな。
ここまでの流れ的に、攻めるのは相手が絡むから、そこを見極める目が必要になるのが難しい、ということが分かると思います。けど、守ることは自分本位に動いたとしても十分に成立しそうですよね?
つまり、「自分にとっての苦手を解消して欠点をなくす」ということであれば、一般人でも自分から取り組めてる、負けないようにするためのカギなんじゃないかと私は思うんです。
守りを固めていれば、たとえ突然攻められたとしても負けることはない。そして、負けることがない態勢を整えてしまえば、それ以降の時間は全てどのように攻めていこうか考え、タイミングを待つ時間に使うことができます。
ということは、守りを固めていれば、攻める案が思い浮かばず、タイミングが分からずとも負けることはない。
もし戦略やタイミングがあれば、その時は勝つことができる。
この状態はまさに、百戦百勝ともいえる万全の状態です。
そして、このように攻めに出ることができたとしたら、それは勝ち筋が見えた時に動いたということです。この状況を、孫子ではこのようにまとめており、現代でも生きる有名な言葉になっています。
原文)勝兵先勝而後求戰、敗兵先戰而後求勝。
書き下し文)勝兵は先ず勝ちて而る後に戦いを求め、敗兵は先ず戦いて而る後に勝を求む。
現代語訳)
勝利の軍は〔開戦前に〕まず勝利を得てそれから戦争しようとするが、敗軍はまず戦争を始めてからあとで勝利を求めるものである。
引用元:金谷治訳注 新訂孫子 岩波文庫 P59
おわりに
第四:形篇の内容はいかがでしたか?
自分から変えることのできる守りを優先することで、負けない態勢を整えることの重要性が分かったのではないでしょうか?
そして、負けることがなければ、逆説的に百パーセント勝てる、というワケですね。なんだか都合のいい話をされている気がしないでもないですが、それでも負けないというのは大きな魅力ですよね。
私たちも何かをしようとするとき、どのように攻略していこうかと考える場面は多いと思います。けれども、その攻略手順の中に自分の力だけでは変えられない要素も含まれているのであれば、先に自分次第で変えることができる要素を変えてから手を付けるのでも遅くはないのかもしれません。
少なくとも、守ることの重要性を理解した今、確実にこれを知る前よりも考え方が広がったはず!これが明日に生きるといいな!
では今日はここまでっ!読んでくださってありがとうございました!
おやすみなさい~~ ꜂( ꜄.ω.)꜄コテン


コメント