孫子は、今から約2,500年前にあたる、紀元前500年ごろの斉国(現中国の一部)で、孫武(書籍内でいう孫子と同一人物)という人物によって書かれた兵法書です。時代を超えて内容が評価され、2,500年もの間、世界中で多くのリーダーから読み継がれてきた孫子は、全部で十三篇から構成されます。
今回はそんな孫子の中から、第一:計篇)を簡単にご紹介!
これはテスト勉強ではありません!
なので、まずは知ることを楽しめればそれでヨシ!ついでにリーダーとして役に立つ何かを学べれば、もっとヨシ!「ふ~ん」っていうような、気楽なきもちで見てみてくださいね♪
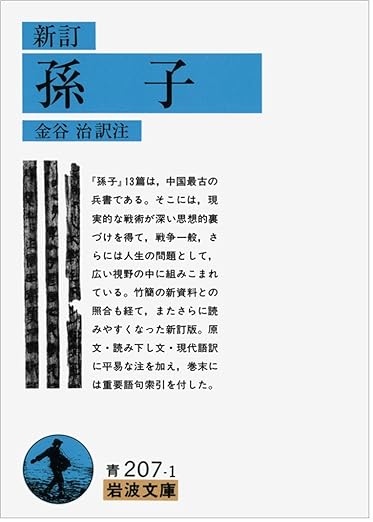
金谷治訳注 新訂孫子 岩波文庫
第一:計篇 結論
戦う前から、勝敗は分かる!
状況をよく観察して、「勝てるポイント」の数を数えよ!
「計篇」という言葉の意味
まずは、「計篇」という名前に含まれる、漢字「計」の意味について見てみましょう。
計は、かぞえる / はかる / はかりごと / はかり / ばかり などの意味を持つ漢字です。
引用元:漢字辞典ONLINE. 漢字「計」の部首・画数・読み方・筆順・意味など
調べて出てきた意味のうち、今回は「はかりごと」という意味が当てはまるような気がしますね~~。
「はかりごと」の意味を持つ熟語として、「計画」などがあります。前もって方法とかを考える、ということですね。
つまり、第一:計篇は、「前もって何かしらを考える章」ってことになります!
そして、兵法書である孫子において前もって考えるものは…そう、勝てるかどうか、です!では次に、戦いに勝てるかどうかはどのように考えるのでしょうか?
五事七計 ~現状を把握するための材料~
孫子では、戦う前の現状整理として、五事七計と呼ばれる要素たちについて考えます。「五事」と「七計」では考える対象が違うので、それぞれ見てみましょう!
五事:自分たちは今どういう状態?
「五事」について、孫子の中では以下のように触れられています。
原文)一曰道、二曰天、三曰地、四曰將、五曰法。
書き下し文)一に曰わく道、二に曰わく天、三に曰わく地、四に曰わく将、五に曰わく法なり。
ついに出てきました、原文!なんだか漢字だけの文章を見ていると、「今やってるの、日本語の文章じゃなくて漢文なんだな~」というきもちになってきますよね(笑)
さて、上に出てきた「五事」は、それぞれ以下の内容を表します。
道 ➡ 政治(組織のまとめ方)
天 ➡ 天候(タイミング)
地 ➡ 土地(今おかれている環境)
将 ➡ 将軍(リーダー)
法 ➡ 軍制(チームにおける規律)
孫子はもともとは兵法書なので、書かれている内容もそのまま読むと国や軍に関連するものになりますね。しかし、これを現代風に置き換えて読んでみるとどうなるか?それぞれカッコ内のような言葉となり、一気に自分たちの生活と身近な言葉になりましたね!
今、自分たちの組織はどのようにまとめられていますか?戦うにあたって、タイミングはどうですか?周囲の環境、よい状態ですか?リーダーは頼れる人ですか?チームの規律は十分ですか?
「五事」に出てくる内容は、このように自分たちの状態を振り返る上で大切な言葉たちなんです!
七計:相手と比べてみてどうですか?
「五事」が自分たちの状態を把握するための要素であったのに対し、「七計」については、孫子の中では以下のように触れられています。
原文)曰主孰有道、將孰有能、天地孰得、法令孰行、兵衆孰强、士卒孰練、賞罰孰明。
書き下し文)曰わく、主孰れか有道なる、将孰れか有能なる、天地孰れか得たる、法令孰れか行なわる、兵衆孰れか強き、士卒孰れか練いたる、賞罰孰れか明らかなると。
「七計」についても、その内容を以下に整理してみましょう。いずれも、自分たちと相手とを比較する内容となっています。
一.君主が人々から支持されているか
(組織の重役がメンバーからの支持を集めることができているか)
二.将軍が有能であるか
(リーダーが有能であるか)
三.天候、土地の状況が優れているか
(タイミング、場面が適切か)
四.法令が正しく執り行われているか
(規律がしっかりとしているか)
五.軍は強いか
(チームとしての力が高いか)
六.兵士がよく訓練されているか
(チームのメンバーにも実力があるか)
七.賞罰がはっきりとした基準に基づき執り行われているか
(何をしたら褒められる、何をしたら怒られる、その基準がはっきりとしているか)
このように「七計」の内容を見てみると、「五事」として把握した自分たちの状態に対し、相手の状態はどうだろうかと考えて、相手と比較するものが多い印象ですね。2,500年前の内容のはずなのに、今読んでみても「なるほどね」と思わせられる点が多いのは、きっと孫子が時代に関わらない勝負ごとの本質を追求した書物だからこそかもしれないですね。
五事七計により、勝てそうかどうか判断
ここまでに、五事七計に基づいた現状把握について説明してきました。
勝負に関わる各要素について、自分たちの状態を把握し、対戦相手の状態とも比較した今、分かることがあります。
自分たちは、相手よりもどの要素で勝っているのか。
自分たちは、相手よりもどの要素で劣っているのか。
自分たちが相手よりも勝るものが多ければきっと勝てるし、劣るものが多ければきっと勝つのは難しい。
これが、孫子でいうところの「戦う前から勝敗は分かる」ということなんですね~~。
おわりに
戦う前から勝敗を知ろうとすることは、ゲームみたいに負けてもすぐにやり直せる世界ならあまり気にしなくてもいいことなのかもしれません。しかし、著者の孫武が生きた時代は、負けてしまえば相手に殺されてしまう時代。だからこそ、実際の行動に移す前に勝敗の結末を把握し、負けないように工夫をこらす文章が記されたのかもしれませんね。
そしてこれは、負けが許されないビジネスの世界でも考え方としては似ているのではないでしょうか。リーダーとしてチームを負けさせないために、その勝負に勝てそうかどうかの予測をしっかりと立てる。今の状態では厳しそうなら、立ち向かうために対策をうち、次の勝負を見据えてまた予測する。
仲間を導くような立場・タイミングであれば、リーダーとして計画的に勝ちに行くためにも忘れずにいたい姿勢ですね。
では今日はここまでっ!読んでくださってありがとうございました!
おやすみなさい~~ ꜂( ꜄.ω.)꜄コテン

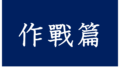
コメント